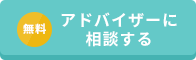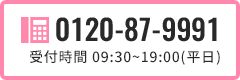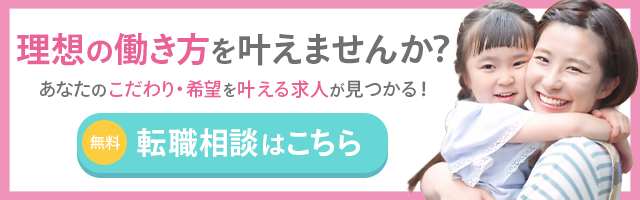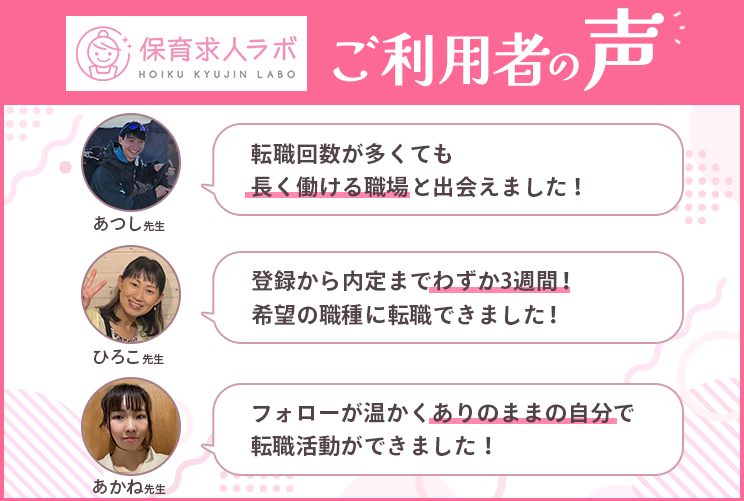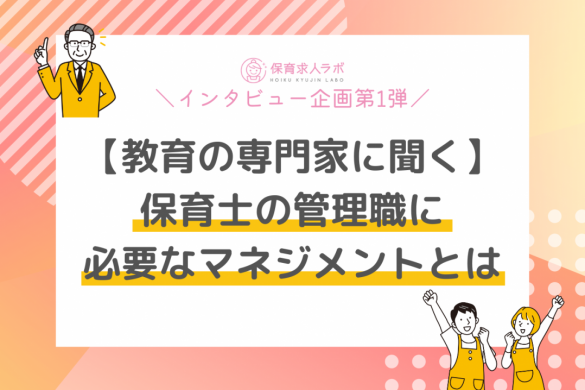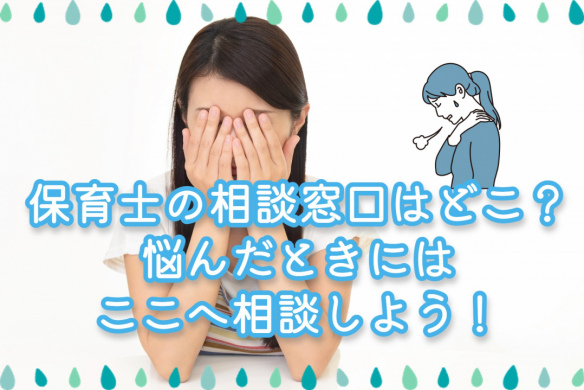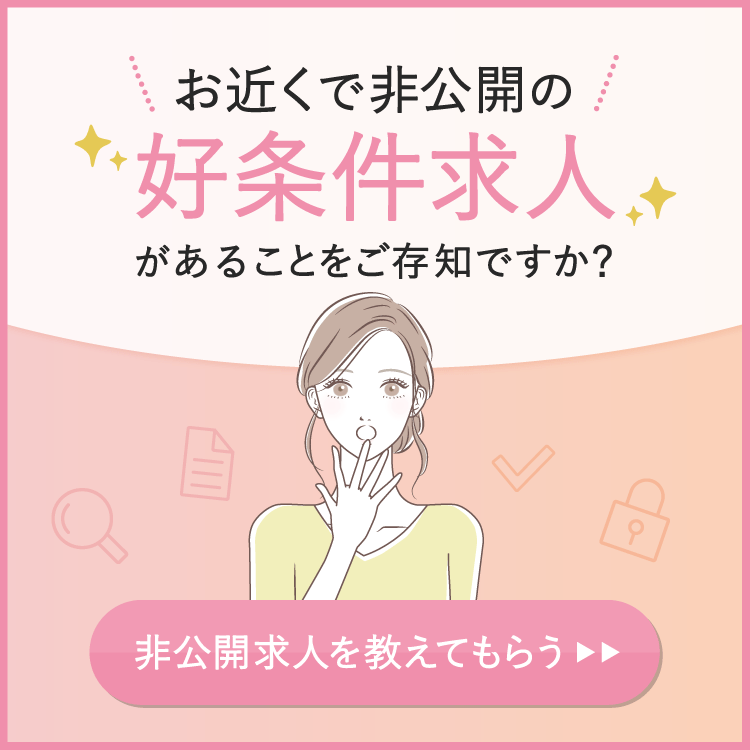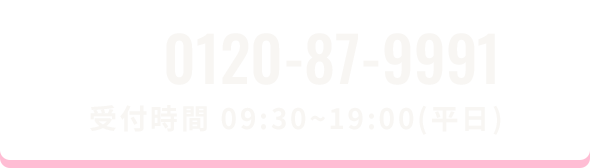お役立ち情報
不適切保育とは?事例や原因、対策を完全解説

不適切保育という言葉をご存じでしょうか。保育園は子どもにとって安心で安全な場所でなければならないにもかかわらず、身体的・心理的に傷つけられる恐れのある保育のことを指します。この不適切保育つまり、行き過ぎた指導を目にしたとき、他の保育士はどのような対策を取るべきなのでしょうか。今回は、保育士の不適切保育の実態とその原因・対策について紹介していきます。
■目次
不適切保育とは?
不適切保育とは、子どもに罰を与えたり、乱暴な関わりをしたり、身体的・心理的に深い傷を負わせる保育のことを指します。
このような保育は、子どもを健全に育成するのにふさわしくありません。
確かに保育士は、子どもの日常生活のお世話を含め、集団生活に適応できるように指導しなければなりません。
しかし、これが行き過ぎた指導となると子どもは心に深い傷を負います。
不適切保育は以下のようなものがあります。
●子どもに不必要なほどの罰をあたえる
●乱暴な言葉を使用する
●意味もなく大きな声で怒鳴る
●置き去り、閉じ込め
●たたく、ける など
全国の不適切保育の実態
こども家庭庁が2023年5月に行った調査の結果、2022年4~12月、全国の認可保育所で不適切保育が914件あったと報告されました。
うち「虐待」と認定されたケースは90件にのぼるとのこと。
確認されただけで900件以上あるため、私達が想像していないような数の不適切保育がまだあることが容易に想像できます。
参照:「保育所等における虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査」の調査結果について|子ども家庭庁
>>>あわせて読みたい「保育士の相談窓口はどこ?悩んだときにはここへ相談しよう!」
不適切保育の事例
2023年 認可外保育施設(宮城県仙台市)の事例
仙台市内の認可外保育施設で、園児に対する不適切な保育が行われていたことが発覚しました。
具体的には、園児への暴力行為(頬をつねる、胸を小突く、逆さまに持ち上げるなど)、事故のリスクが高い行為(放置や不適切な遊び方)、午睡中の服薬、日常的に下着姿で昼食を取らせる行為、泣いている園児の放置、不適切な声かけによる精神的な圧力などが挙げられます。
2023年 認定こども園(福島県会津若松市)の事例
会津若松市の認定こども園で、園児を遊具の狭い空間に閉じ込めたり、名前を呼び捨てにして乱暴な言葉を使うなど不適切な保育が行われていたことが判明しました。
複数の保育士によるこれらの行為が認められたため、県は再発防止のため行政指導を行い、改善計画の提出を求めています。
2023年 認可保育園(愛知県名古屋市)の事例
名古屋市は、認可保育園で保育士が園児にご飯を口に押し込むなどの虐待を行ったとして、改善勧告を行いました。
同園は2015年度にも同様の指導を受けており、今回の虐待は2023年4~9月に発生し、女性保育士4人が関与したと認定されています。
不適切保育が起こる原因とは

不適切保育はいかなる理由であれ起こってはならないことであり、子どもを傷つけるなど言語道断です。
しかし、その原因や背景を知ることで、少なからず対策を講じることができるでしょう。
①ストレスが大きい
保育の現場は子どもの命を預かっているため、非常にストレスが大きく、責任の重い仕事になります。
また人間関係も複雑で、子どもや保護者、地域の方々、習い事の先生、同僚、管理職の先生など、関わらなければならない人が大勢います。
そのため、人間関係のストレスも大きいといえるでしょう。
②人手不足で過重労働
昨今の保育士不足では1人にかかる仕事量は非常に多く、負担となっていることが考えられます。
そうなると休む暇もないため、子どもとしっかり向き合い、保育をするという余裕がなくなってしまうのかもしれません。
③保育園の指導方針が行き過ぎている
先輩保育士、もしくは管理者が行き過ぎた指導方針であると、従わざるを得ない可能性も出てきます。
ですが子どもを威圧し、言うことを聞かせようとすることは、子どもをコントロールしようとしていることと一緒です。
子どもを1人の人間として尊重していれば、このような指導は出てこないでしょう。
④保育士のスキル不足
ただ単に保育士としてのスキルが不足していることが考えられます。
子どもを叱るにしてもただ感情に任せて怒鳴るのと、理解できるように指導し、叱るのでは全く意味合いが異なってきます。
保育士は、不適切保育の背景にこのような原因があることを理解し、行き過ぎた指導をしないように注意する必要があります。
>>>あわせて読みたい「【保育士必見】より良い保育のために保育士が心がけることって?」
不適切保育がもたらす児童虐待とは?

不適切保育は、場合によっては虐待に当たる可能性があります。
そうならないためにも非常に注意が必要であり、子どもの成長に悪影響を及ぼすことを知っておかなければなりません。
どのようなことが虐待になるのか、改めて確認しておきましょう。
●身体的虐待
殴ったり、蹴ったり、叩いたりすることは身体的虐待です。
縄で縛ってお仕置き部屋などと称して部屋に閉じ込めることも、これに当てはまります。
●心理的虐待
子どものことをあからさまに無視したり、脅したり、子ども同士で差別扱いすることは心理的虐待です。
「子どもの心を死なせてしまうような虐待」と理解しておくと良いでしょう。
●ネグレクト
トイレの世話をしなかったり、意味もなく子どもに給食を与えなかったりすることは、ネグレクトです。
送迎バスなどでの放置などもこれに当てはまり、適切な処置を怠れば命に危険が及ぶこともあります。
●性的虐待
子どもへの性的な嫌がらせや身体を触ったり、触らせたりすることは、性的虐待です。
異性への児童に行われることが多いといわれています。
行き過ぎた指導は単なるしつけなのか、虐待にあたるのか、非常に線引きが難しいところです。
子どもが嫌な思いをしていないか、自分がされたら嫌かどうかを判断基準として考えると分かりやすいかもしれません。
不適切保育を無くすための対策

不適切保育を見かけたら、あなたはどうしますか?
また、もしも自分が行った指導が行き過ぎているようであれば、あなたはそれに気づくことができるでしょうか。
ここでは、不適切保育を無くすための対策を紹介します。
子どもに完璧を求めない
子どもは、まだ発達段階の途中にあります。
保育園や家庭、その他のいろいろな場所で経験を積み、さまざまなことを学んでいきます。
子どもに完璧を求めず「ここまでできれば、まぁよしとしよう」と長い目で見守ってあげることも大切です。
虐待はどのような場面で起こるか理解しておく
虐待が起こりやすい場面はどのようなところかご存じでしょうか。
それは、子どもと保育士が2人きりになる場面です。
例えば、個室やトイレ、保育室で二人きりのときが挙げられます。
このような場面は注意して他の保育士が様子を見てあげたり、気を配っておいたりすることも大切です。
不適切保育に賛同・同調しない
不適切保育が日常的に行われると、それが当たり前となってしまうことがあります。
特に新人さんは、疑問に思っていても立場上なにも言えずにいることもあるでしょう。
「この保育のやり方はまずいのではないか?」と疑問に思ったことは同調せず、自分の保育の中に取り入れないように、気を付ける必要があります。
心の余裕を持って子どもと向き合う
仕事が忙しかったり十分に休むことができず心に余裕がなくなってしまうと、子どもにきつく当たってしまうことも…。
それでは質のいい保育につながらないため、リフレッシュして心に余裕を持たせてから子どもと向き合うようにしましょう。
自分自身の保育を見つめ直す
不適切保育をしてしまったかも…と感じたら、一度立ち止まって、自分の保育観についてじっくりと考え見つめ直してみましょう。
感情的になってしまうと、どうしても相手が見えなくなってしまいます。
目の前の子どもをしっかりと見て、自分の保育はどうありたいのか、自分自身を見つめ直してみましょう。
必要であれば外部機関に連絡をとる
不適切保育や虐待が疑われるとき、外部機関に連絡する勇気を持つこともときには必要です。
匿名で通報もできるため、一歩踏み出して子どもを助ける勇気を持ってください。
児童相談所虐待対応ダイヤル:189
雰囲気が変わらなければ転職も検討
職場の雰囲気が変わらなければ、転職も検討にいれてもいいかもしれません。
なにより、子どもを傷つけるようなことはあってはいけませんし、そのような職場にしがみつく必要もありません。
保育見学や面接を通して、その保育園の指導方針をきちんと確認したうえで、自分に合った保育園を見つけましょう。
まとめ
保育士の不適切保育は、虐待となる可能性があります。
そうならないためにも、自分自身に余裕をもって、目の前の子どもに対して自分のやりたい保育は何なのかを見つめ直しましょう。
そして、もし、周囲に不適切保育をしている保育士がいたら「NO!」という勇気を持ち、ぜひ子どもを守ってあげてください。
また、職場の雰囲気が変わらなければ、転職を検討することも一つの方法です。
『保育求人ラボ』『保育求人ラボ+』では、専門アドバイザーが求人提案や面接対策、条件交渉までサポート。
「どうやって転職活動を進めればいいかわからない」「自分に合った園を探す方法を知りたい」とお悩みの方はぜひお気軽にご相談くださいね。