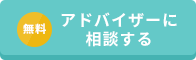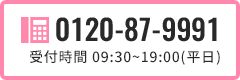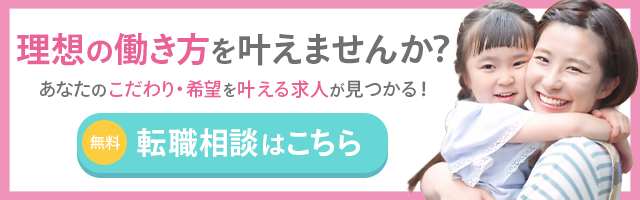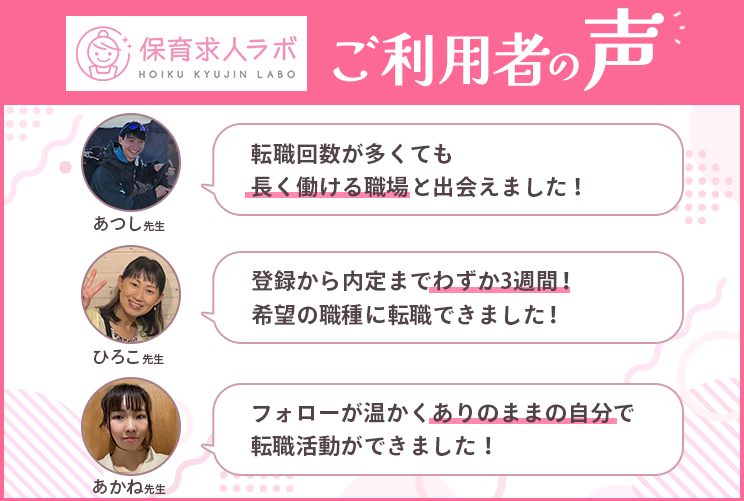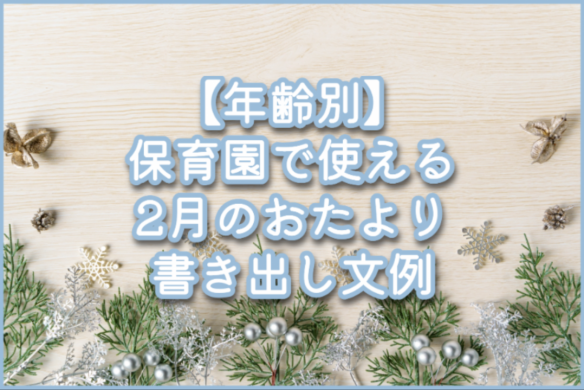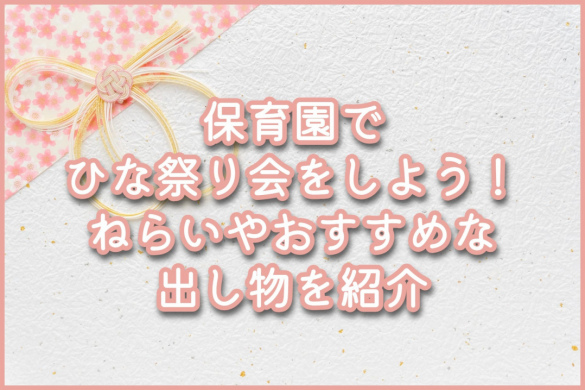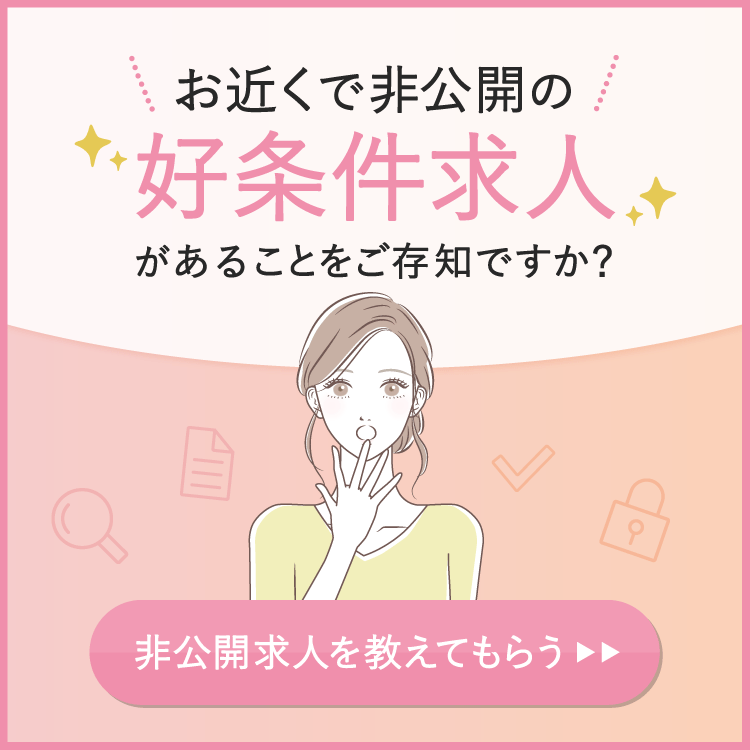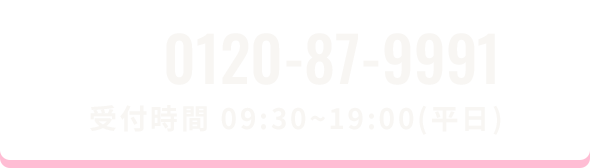お役立ち情報
建国記念の日とは?由来や意味を子どもに分かりやすく説明しよう
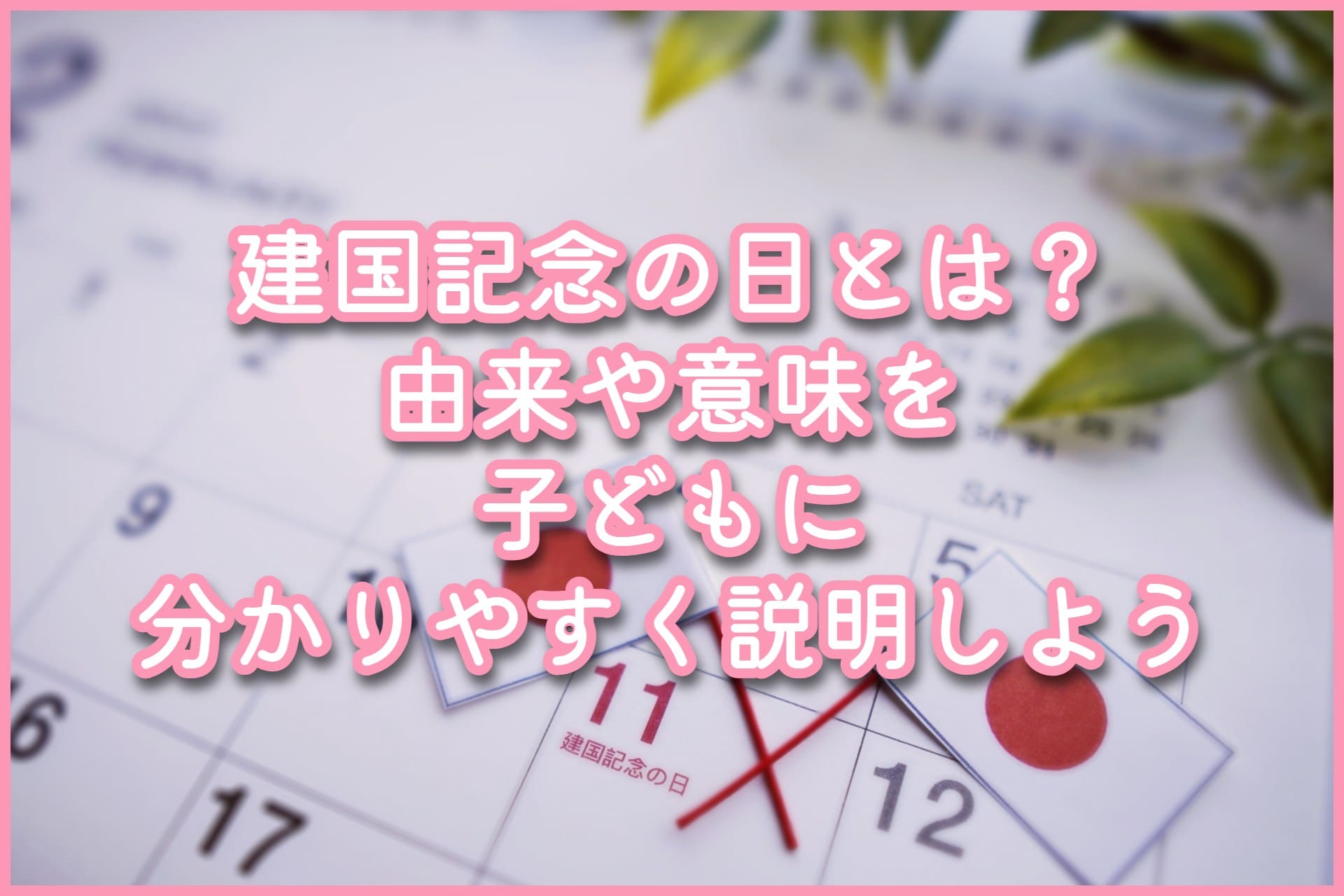
保育園で子どもに「建国記念の日ってどんな日?」と聞かれた際、どのように説明しますか?建国記念の日の由来や詳しいことは分からない、という保育士は多いのではないでしょうか。今回は、子どもに分かりやすく建国記念の日を説明する方法やおすすめの過ごし方について解説します。
■目次
建国記念の日(2月11日)ってどんな日?
建国記念の日とは、”建国をしのび、国を愛する心を養う日”として定められた国民の祝日です。
言い換えれば、日本が建国されたことをお祝いし、国を大切に思う気持ちを養う日という意味のある日になります。
建国記念の日には、毎年多くの神社で式典が行われたり、東京で奉祝パーティーが行われたりと、さまざまなイベントが行われます。
また、この建国記念の日は世界中にあり、”独立記念日”や”革命記念日”など、その国の経緯に由来して命名されているのが特徴です。
特に7月4日のアメリカ独立記念日は、日本のニュースなどでも取り上げられ、耳にする方も多いのではないでしょうか?
どの国においても、建国記念の日は大切な、特別な日として親しまれています。
参照:内閣府|「「国民の祝日」について」
建国記念の日|由来や『建国記念日』との違いとは?

建国記念の日は、昔の祝日である”紀元節”に由来しています。
この紀元節は、初代天皇の神武天皇が即位した日が紀元前660年2月11日だったことから、1873年2月11日に定められたようです。
第二次世界大戦敗戦後の1948年まで親しまれていた祝日でしたが、日本を占領していたGHQの意向により廃止されてしまいました。
その後、国民の間で”紀元節”復活の動きが高まり、日本の建国を記念する日として、1966年2月11日に現在の”建国記念の日”が制定されたのです。
●『建国記念日』との違い
建国記念の日は、『建国記念日』と間違って呼ばれることがあります。
世界的に建国記念日というと、”国ができた日を祝う記念日”として制定されています。
ですが日本は、建国がいつ行われたのかが明確に分かっていません。
そのため、日本が”建国された日”とは関係なく、ただ単に建国されたという事実をお祝いするという考えにより”建国記念の日”となったようです。
建国記念の日|子どもに分かりやすく説明するには?

子ども達に建国記念の日がどのような日なのか、ということを理解してもらうために、できるだけ難しい言葉は噛み砕いて伝えるようにしましょう。
建国記念の日について子どもに分かりやすく説明する方法は、以下の通りです。
- <乳児向け>
- 2月11日は建国記念の日といって、みんな住んでいる日本という国のお誕生日をお祝いする日です。
日本のことをもっと大切にしよう、という気持ちを持って過ごそうね。
- <幼児向け>
- 2月11日は、建国記念の日です。
この日は、日本という国ができたことを、みんなのお誕生日のように「おめでとう!」とお祝いする日です。つまり、日本のお誕生日をお祝いするということ。
建国記念の日には、みんなで日本地図を見たり、みんなが知っている日本のことについて話し合ってみよう。
乳児に向けて説明する際は、あわせて日本の国旗などを見せてあげると良いでしょう。
そうすることで、日本という国のイメージが湧きやすくなるかもしれません。
幼児には、建国記念日について簡単に説明したうえで、日本のことについて話し合う機会を設けてみましょう。
意外にも、国旗のことや文化のこと、スポーツのことなど、色々な話が子ども達から聞けるかもしれません。
建国記念の日|保育園でのおすすめな過ごし方

保育園での建国記念の日のおすすめな過ごし方は、以下の通りです。
日本地図を見てみる
日本地図を見て、自分たちが住んでいる日本がどんな国かを考える機会を作りましょう。
日本が都道府県に分かれていることや海に囲まれた島国であることが地図から読み取れ、子どもにとって新しい発見につながるかもしれません。
また、世界地図を見て、その中から日本を探したり、他の国とどんな違いがあるのかを比較してみるのもおすすめです。
日本史の絵本を読み聞かせする
日本史に関する絵本の読み聞かせも、建国記念の日にぴったりな過ごし方です。
絵本ならではの絵や文章を通して、日本について分かりやすく学ぶことができます。
日本史以外にも、日本の神話にまつわる絵本の読み聞かせもおすすめです。
まとめ
今回は、子どもに分かりやすく建国記念の日を説明する方法やおすすめの過ごし方について解説しました。
”建国をしのび、国を愛する心を養う日”として定められた国民の祝日。
建国記念の日には、日本のことを話し合ったり、日本史にまつわる絵本を読み聞かせしたりと、日本についてより深く理解できるような過ごし方をしてみましょう。
『保育求人ラボ』ではレクリエーションに力を入れる園を多数取り扱っています。
季節感や行事を大切にした保育を行いたい方、行事に力を入れる園で働きたい方は、ぜひ『保育求人ラボ』に登録して、理想の職場を見つけてくださいね。