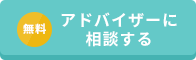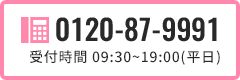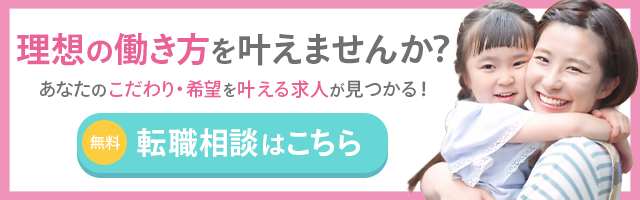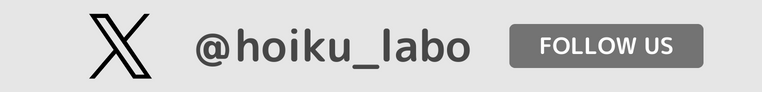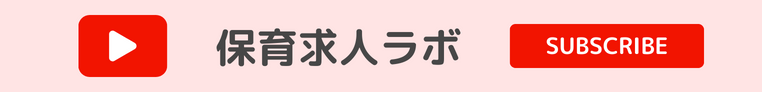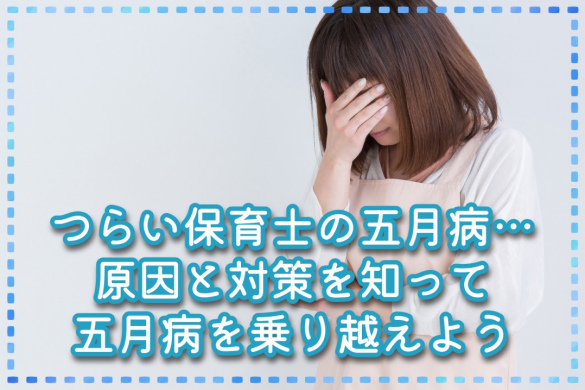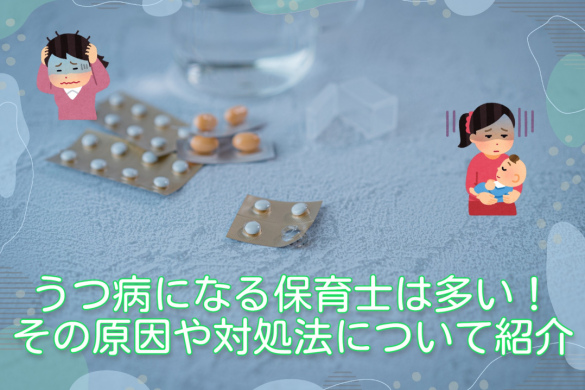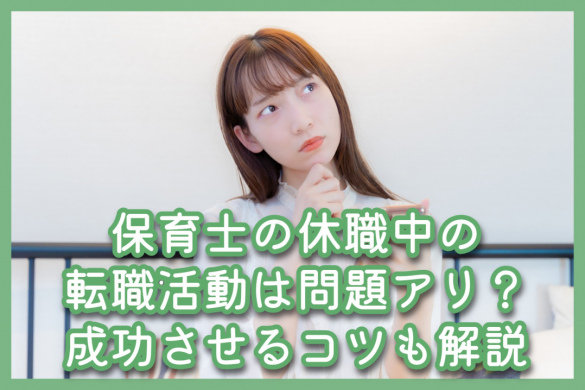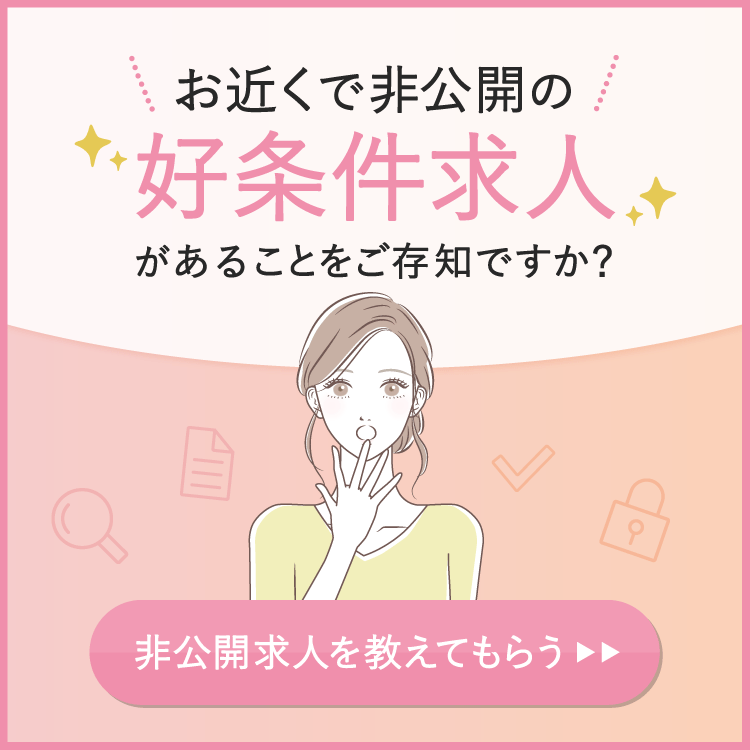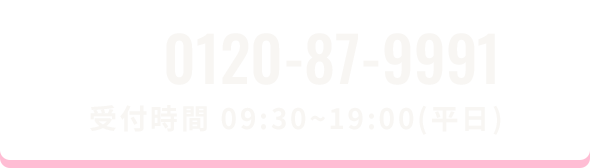お役立ち情報
保育士が知っておきたい適応障害について解説!注意すべきサイン

毎日さまざまな業務に追われ忙しく働いている保育士さんは、ストレスを抱えやすく心身に支障をきたすことがあります。心の病の中でも、適応障害は保育士でなる人も多く、まだ症状がない人も知っておくべき疾患といえるでしょう。今回は、保育士が知っておきたい適応障害の特徴や対処法について解説します。
■目次
適応障害は保育士の身近な疾患

保育士は、精神的な疾患にかかりやすい職業といえます。
それは、一人に対する仕事量の多さや気を遣う人間関係など、ストレスとなりやすい要因がたくさんあることが原因だと考えられます。
精神疾患の中で、適応障害は保育士にとても身近な疾患です。
しかし、自分が適応障害かもしれないと思っても、受け入れられなかったり認めたくなかったりするかもしれません。
まずは、適応障害とはどんな病気なのかを正しく理解し、恐怖や不安を払拭することが大切です。
次の項目で、適応障害について理解を深めていきましょう。
適応障害ってどんな病気?
適応障害とは、ある特定の出来事や環境が原因でそれがストレスとなり、情緒や行動面で生活に支障をきたす症状が現れるものです。
ストレスを感じる度合いは個々で異なりますが、他の人からすると大したことがないことでも、本人にとっては重大で抑うつ気分や不安などが明らかに正常の範囲を超えている状態をいいます。
症状としては、抑うつ気分、強い不安や心配、焦り、緊張、暴飲暴食、無断欠席、攻撃的になるなどがあります。
適応障害とうつ病の違い
適応障害の症状と似ているものにうつ病があり、気分が落ち込みやすく、イライラするなどの部分では同じです。
適応障害とうつ病の違いは、原因から離れたときに症状が改善するかどうかという点にあります。
適応障害の場合、ストレスとなっている原因から離れると症状が落ち着くことが多いですが、うつ病の場合は環境が変わっても憂鬱な気分や興味関心の低下、食欲不振などが持続的に現れます。
適応障害はどうやって治療する?
適応障害には明確な原因(ストレス因)があるため、まずはそれを取り除くことが一番の治療です。
例えば、職場の人間関係がストレスになっている場合、あまり人と関わらなくて済むようなポジションに環境を調整したり、休職したりといった方法が考えられます。
また、ストレスを上手に受け止めストレス耐性を作っていくために、本人の適応力を高めていくことも重要です。
必要に応じて薬を服用して経過を見ていきます。
>>>あわせて読みたい「うつ病になる保育士は多い!その原因や対処法について紹介」
保育士が注意すべき適応障害のサイン
適応障害の原因となりうるものには、仕事・人間関係・恋愛・家庭などが挙げられます。
その中でも保育士は、仕事内容・職場の人間関係・長時間労働・仕事量の多さなどがストレスとなっていると考えられるでしょう。
先輩から怒られる、仕事を押し付けられる、休みが取れない、子どもが言うことを聞かないなど、一見よくありそうなことでも人によっては強いストレスとなって心身のバランスを崩してしまいます。
例えば、このような悩みや辛い症状が継続的にある場合は注意が必要です。
●職場に行くことに強い不安や恐怖感がある
●仕事に対して無気力になった
●子どもの前で笑えなくなった
●ぼんやりすることが多い
●よく疲れていると言われる
●理由もなくイライラしてしまう
また、適応障害は、ストレスの要因となっているものから離れると症状が落ち着き、普段通りに過ごせることが多い傾向にあります。
仕事が終わると元気になったり、プライベートでは明るく過ごせたりすることが適応障害の特徴です。
そのため、他の保育士から「怠けている」「意欲がない」などと思われることもあるかもしれません。
しかし、このような症状に気付いたときにはもう既に適応障害になっている可能性も考えられます。
他人に何を言われても、自分が「何か変だな・・・」と思ったら無理をせず早期に対処していくことが大切です。
>>>あわせて読みたい「新人保育士の悩みとは?悩みが深刻化しないよう心がけるべきこと」
保育士がもしかして適応障害かな?と思ったら

適応障害のような症状がある場合は、以下の方法で対応しましょう。
まずは専門医に相談しよう
適応障害かどうかは自分では判断できないため、精神科や心療内科などの専門医を受診しましょう。
受診すると診断書がもらえて、休職や退職をする理由になります。
また、必要に応じて薬を服用していきます。
薬の種類や作用の強さはさまざまで、症状を見ながらそのときに適切な薬を処方してくれるでしょう。
よく眠れない場合は睡眠薬を処方してくれます。
ここで大切なのは、受診をためらわないことです。
精神科や心療内科を初めて訪れる場合は不安になるでしょう。
通い慣れていない場所に行くことに抵抗があるのも無理はありません。
また、病院に行くときはストレス要因から離れているため普段の様子と変わらないことも多く、本当に病院に行くべきなのか疑問に思ってしまうかもしれません。
そんなときでも、受診して損はないと信じて一度病院を訪れてみることが大切です。
休職してゆっくり休もう
適応障害はストレスから離れることが重要なため、休職は立派な治療の一環だといえます。
私たちが思っている以上に適応障害は厄介ですぐには治りません。
「今日は調子いいな」と思っても、またすぐに気分が落ちることもあります。
そのため、医師の指示に従いながらゆっくり休むことが何よりも大切で、休職という選択はとても有効な手段となります。
それでも、もしかしたら周りはそれをよく思わないかもしれません。
しかし、そのまま無理して仕事を続けていても辛さが増すだけです。
休職してみると余裕が生まれ、辛かったことや悩んでいたことを客観的に整理することができます。
自分が何に反応していたのかを知ることができれば、適応障害の克服に繋がります。
思い切って環境を変えてみよう
退職するのは勇気がいりますが、適応障害になったら働く環境を変えるのが一番よい方法です。
可能であれば、思い切って新しい職場に移るべきです。
退職しても、今まで積み重ねてきた経験や保育士としてのキャリアが失われるわけではありません。
環境を変えることでまた保育士として活躍できる可能性は大いにあります。
今の職場がたまたま合わなかっただけで、違う職場に行けば生き生きと働けるかもしれません。
今の職場に固執せず、自分らしく働ける居場所を見つけましょう。
>>>あわせて読みたい「主任保育士ならではの悩みとは?辞めたいと思う前に解消しよう!」
保育士が適応障害になっても自分を責めないで!

”適応障害は自分の弱さが原因”と勘違いする人がいますが決してそうではありません。
「自分には適応能力がないんだ」「自分が無能だからだ」などと思わないでください。
適応障害は、適応できないのではなく、適応しようと頑張りすぎている結果だといえます。
子どもの命を預かっている責任の大きい保育士だからこそ、一生懸命になりすぎてしまうのです。
大事なのは、自分を責めるのではなく、自分で自分を守る選択をすることです。
今は納得できなくても、「あのときこの選択をしてよかった」と思える日がきっと来ます。
そして、辛い経験はのちに誰かのためにもなり得ます。
苦しさがわかるからこそ、優しい心で人に接することができるのです。
まとめ
今回は、保育士が知っておきたい適応障害の特徴や対処法について紹介しました。
仕事上のストレスに悩む保育士はとても多くいます。適応障害になってしまったとしても、珍しいことではないかもしれません。
自分を責めず、ゆっくりと休みながら少しずつ次のステップへ踏み出していきましょう。
保育士さんの転職サポートは【保育求人ラボ】

【保育求人ラボ】は専門のアドバイザーがあなたに合った保育園・幼稚園の求人をご提案させていただきます。ご不安な点やご希望などしっかりとヒアリングさせていただき、サポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合せください。
保育系ハイキャリア転職なら【保育求人ラボ+】
保育求人ラボ+(保育求人ラボ プラス)は、保育系管理職(園長職・主任職等)限定のハイキャリア向け転職サービス。ハイキャリア専門のアドバイザーが、次のステージに挑戦するサポートを提供いたします。「自分の市場価値が知りたい」「現状のキャリアで管理職は可能か?」などの相談からでもOK!まずはお気軽にお問い合せください。
Instagram・TikTok・X(Twitter)・YouTubeにてお役立ち情報更新中!
フォロー・いいね・コメントよろしくお願いします♪